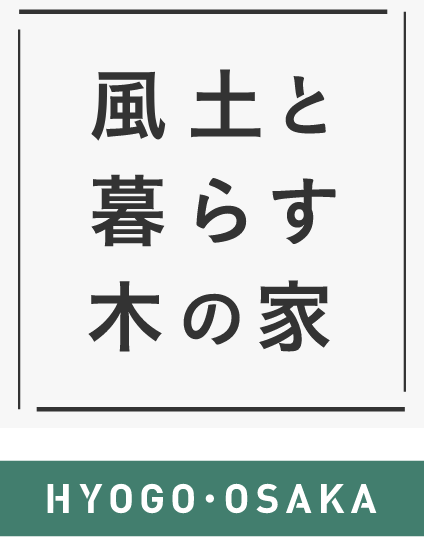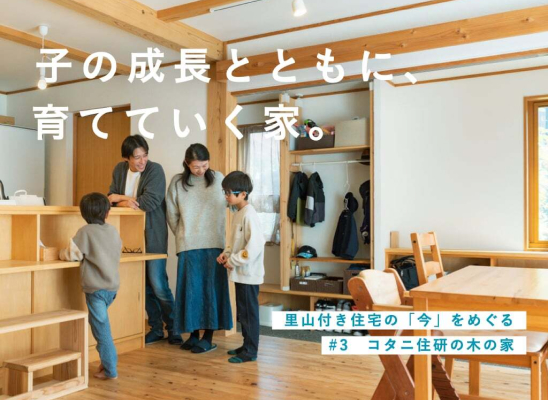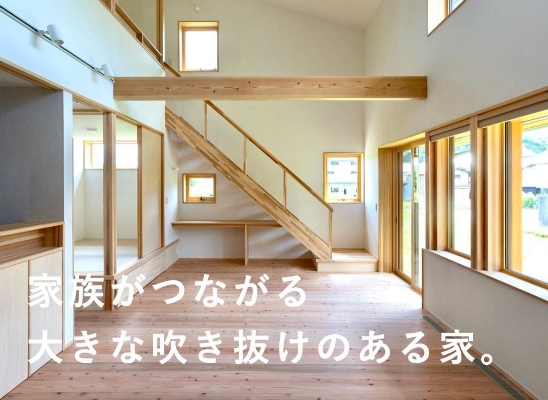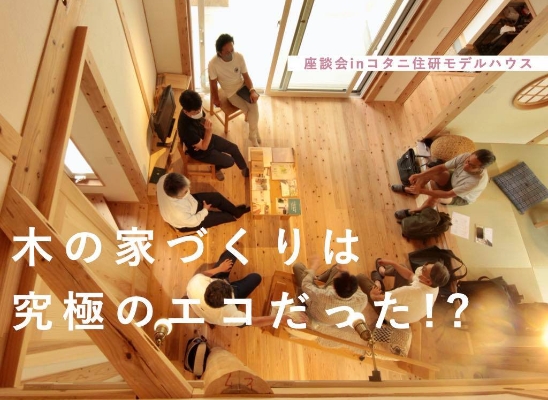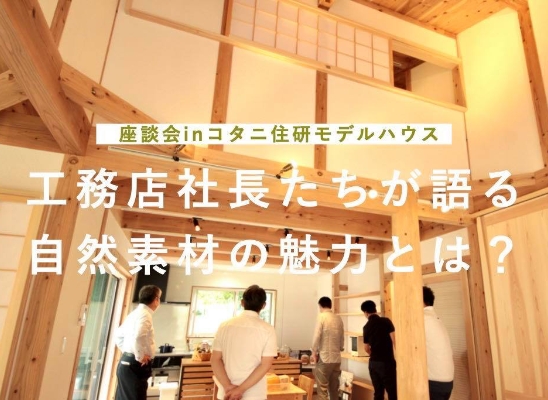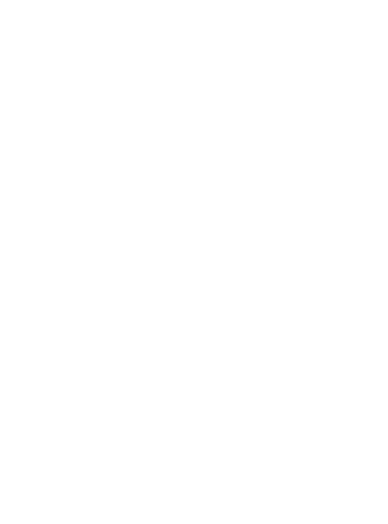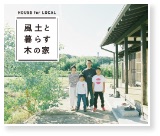Column
地域の土で家をつくる
HOUSE for LOCALに参加する工務店は、できるだけその地域にある材料で家づくりをしたいと考えている。前回は丹波篠山市の林業所を訪ねて、ローカルの「木」を使った家づくりについて考察した。今回は、ローカルの「土」で建材をつくり活用するつくり手を訪ねるべく、淡路島へ視察に行った。その様子をレポートしていく。

淡路瓦の屋根、淡路島の木材を使った家。
淡路島の土産業を巡る
今回の視察は「土」がテーマ。日本三大瓦のひとつである淡路瓦で有名な淡路島には、瓦の他にもタイルや土壁など、土を使った産業が多くあるという。今回はHOUSE for LOCALのメンバーで淡路島へ向かい、瓦づくりの大栄窯業さん、土壁づくりの近畿壁材さん、そして淡路島産の素材を使った家づくりを追求している建築設計事務所のヒラマツグミさんを訪ねた。
瓦屋根の景色を復活させたい
淡路瓦のメーカーは多数あるが、今回は近年革新的な活動を積極的に行っていると話題の大栄窯業さんを訪ね、代表の道上大輔さんにお話を伺った。

大栄窯業のショールームで代表・道上さんの熱いお話を聞いた。
瓦は1400年前に中国から伝来した。当時の日本では茅葺屋根が主流で瓦は贅沢品だったが、徳川8代将軍吉宗が瓦を一般大衆化させ、都市を不燃化しようとした。この時に編み出されたのが現在の瓦の形状である。
以下の写真からもわかるように、瓦には山と谷がある。山に降った水が谷へ落ちて流れるという自然の摂理に適った普遍的なデザインになっている。山と谷があることで空気層ができ、通気が良くなり、瓦を固定する野地板が結露しない。また、このアールによって傷がつきにくくなっている。さらに、和瓦の曲率は1.4141:1の比率で白銀比(大和比)と呼ばれ、西洋の黄金比よりも日本人に馴染み、美しいと感じられる比率になっている。

大栄窯業の看板商品である「銀古美(ぎんふるび)」(左)はとても薄く、一般的ないぶし銀(右)と比べて濃い色合いとなっている。
また、良い意味で規格化されており、1坪の屋根に対して53枚か56枚葺くのがJIS規格となっている。耐久性としては100年以上持ち、昨今のヒョウ被害ではガルバリウム鋼板屋根や太陽光パネルが多大な被害を受けた一方で、瓦屋根の被害はほとんどなかったことからもその堅牢さをうかがえる。1枚割れたらそこだけを取り替えれば良く、古いものと新しいものを混在させて使えるというサスティナビリティの観点からも優れた建材だ。
一方で、瓦は「重い」「高い」「厚くてデザインが悪い」といった理由から、家づくりにおいて敬遠されるようになった。実際、平成4年から令和4年の間に淡路瓦の生産量は90%〜95%も減少したという。もはや瓦は「オワコン」と言われたこともあった。

近年製造されているいぶし銀の瓦と、古来の火窯で焼いた瓦では経年変化の風合いが違う。いぶし銀はムラのある廃れ方をしないので、美しくない。
外国人から見た現在の日本は「風景に特徴がない」と言われるが、それは瓦文化が失われてしまったからではないかと道上さんは語る。20世紀の画家・東山魁夷が描いた京都の景色と、同じ場所で撮られた現在の景色を比較するとその違いは一目瞭然だ。やはり日本の風景には瓦屋根がよく似合う。それを復活させたいと道上さんは提唱している。
そのような思想のもと開発されたのが、「銀古美(ぎんふるび)」というシリーズである。土を焼いただけの素朴な古代いぶし色が特徴で、自然なエイジングが期待できる。役物をあまり使わないことでコストを抑えることができ、他の屋根材と十分に競争できる価格帯で提供している。実際に国内外の建築家からも大きな反響があるという。この銀古美で日本の美しい風景を継承していきたいという熱いお話を伺うことができ、そんな思想やものづくりに共感した。

大栄窯業の工場内。瓦専用のベルトコンベアが張り巡らされている。

焼き上がった瓦が窯の中に整然と並んでいる。
土100%の壁づくりへの挑戦
大正元年創業の老舗メーカー・近畿壁材さんにも訪問し、代表の濵岡淳二さんにお話を伺った。

近畿壁材さんが2023年に開業された「土のミュージアム SHIDO」。
伝統的な土壁は、土に加えて砂や藁をすき込んで、自然素材のみでつくられていた。一方で、近年は生産性を高めるために固化材としてセメントを加えることが増えてきた。しかし、セメントを混ぜ込むとリサイクルが難しくなる。セメントの入ったものを焼いてしまうと、土に還らず産業廃棄物になってしまうのだ。
そこで近畿壁材さんでは、できるだけ土100%に近い壁材の開発に取り組んでいる。のちにリサイクルすることを前提に、自然素材のみでつくり、トップコートを塗って仕上げ、使い終わったら崩して再利用できるようにするというアプローチだ。土壁がリサイクルできるようになれば、CO₂の排出量削減にもつながると期待できる。
淡路島といえば瓦産業が有名だが、「土」屋は瓦屋が使えない土を活用して壁材をつくってきた。近年は新たな試みとして「土のミュージアム SHIDO」という施設もオープンし、土について気軽に知り、触れることができる場所となっている。ここではさまざまな土壁の色やテクスチャーを体感でき、希望に合わせたサンプルづくりも可能だという。
さらに、未利用資源を混ぜ込むといったチャレンジも行われている。たとえば繊維業の方なら糸を、ガラス関連の方なら廃ガラスを土壁に混ぜ込むなど、独特の質感を生み出す可能性があるという。

こちらも敷地内にある、土だけでつくられた小屋。様々なワークショップが企画されている。
淡路島産の素材で家をつくる
最後に紹介するのは、淡路島の素材を活かした家づくりを追求する建築設計事務所・ヒラマツグミさんだ。淡路瓦や土壁をはじめ、林業のない淡路島であっても地域で木を切り、製材して淡路島産の木材を使うなど、地域に根ざした家づくりを実践している。
代表の平松克啓さんにお話を伺いながら、ヒラマツグミの事務所や平松さんのご自宅を案内していただいた。それらの建物は、大栄窯業や近畿壁材の材料を用いて実験的に建てられており、淡路島にある身近な素材でつくられた、建築の本質的なあり方を垣間見ることができた。

ヒラマツグミ事務所脇にある小屋。小屋のプロポーションに合うように工夫して瓦が葺かれている。

ヒラマツグミ事務所の2階には大空間が。ここで壁材の実験をしている。
大栄窯業の道上さんが語った「建築の『築』という漢字には、竹・土・瓦・木という素材が含まれている」という言葉にはっとさせられた。これらは、かつての日本の家づくりを支えた基本素材であり、日本の風景をかたちづくる根幹でもある。これは、日本の建築業界にいる私たちにとって非常に重要な気づきであり、視察に参加したメンバー全員がその意義を実感していた。
特に、スタッフ3名で参加されたフクダ・ロングライフデザインの代表・福田さんが「当社の名前(ロングライフデザイン)からして、普遍的な素材である瓦や土を使った家づくりを今一度見直したい」と語っていたことが印象に残っている。
その地域の土でできた瓦や土壁を取り入れた住まいづくりを通して、風土に根ざした美しい風景と文化を次の世代へとつないでいくこと。その大切さを、今回の視察で改めて深く実感することができた。