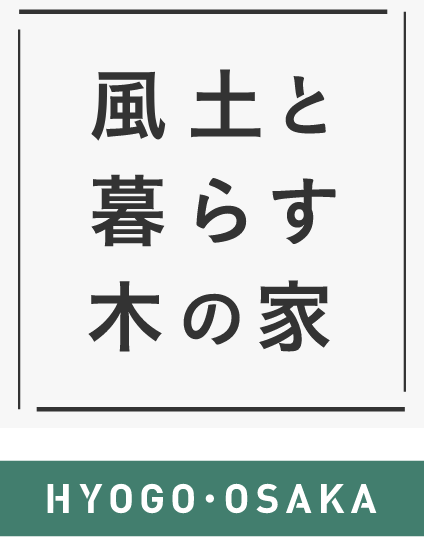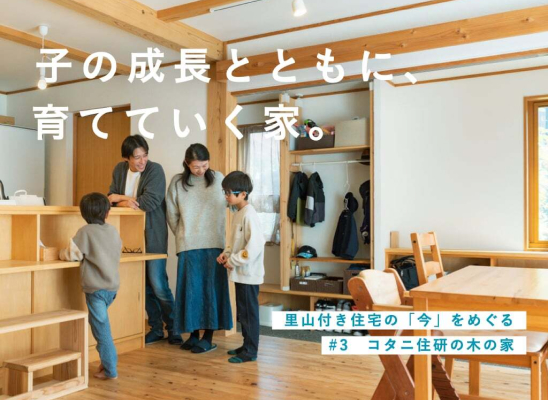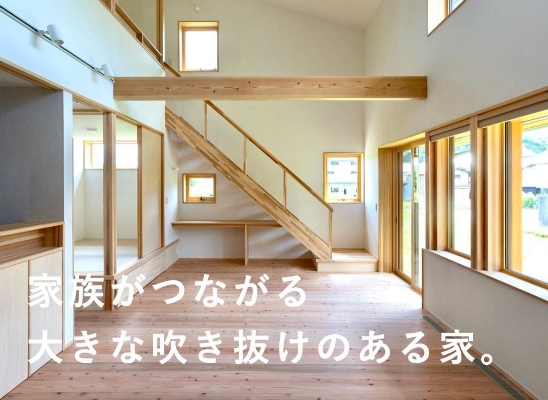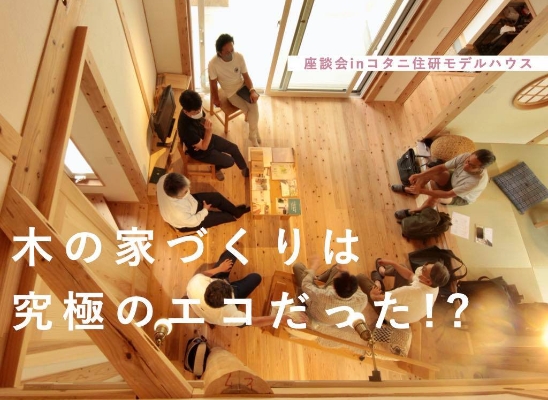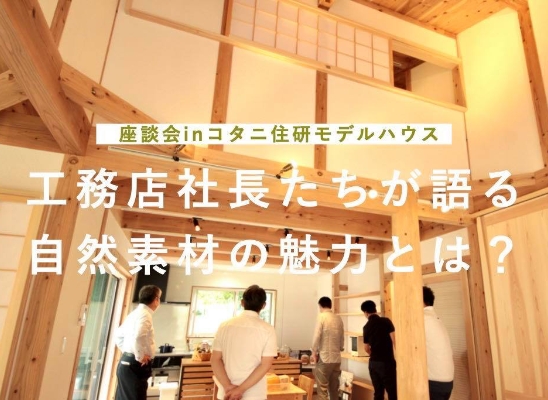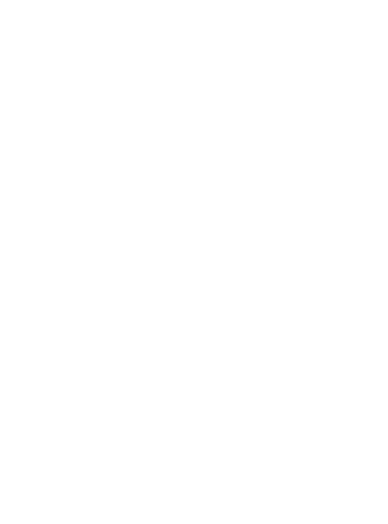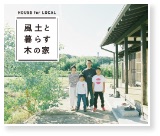Column
地域の「石」とともにある家づくり
HOUSE for LOCALに参加する工務店は、その地域に根ざした素材をできるだけ活かした家づくりを志している。これまで「木」や「土」に焦点を当てて視察を重ねてきたが、今回のテーマは「石」。兵庫県高砂市で、竜山石を取り入れた家と採石現場を訪ねた。
竜山石と暮らす家
訪ねたのは、あかい工房が2019年に手がけた高砂市の住宅。背後には、竜山石の採掘跡がダイナミックな景観をつくり出していた。「この岩肌を眺めながら暮らしたい」という施主の思いがかたちになった家だ。

かつて採掘場だった山の壮観を背景に佇む木の家
印象的だったのは、リビングの主な開口部が北側に設けられていたことだ。窓の外にはかつて石を切り出していた山肌が広がり、各所に設けられたスリット状の窓からは森の緑も切り取られる。敷地の特性を読み解きながら、施主の希望する竜山石の景観を取り込んだ設計となっていた。
「南向きの家」が一般的なセオリーとされることが多いが、どんな環境のどんな家でも単純に南に向けていればいいという訳ではないと、この家は教えてくれた。

採掘跡を切り取る北側の採光窓

2019年の竣工時に撮影された写真
外構にも竜山石を利用したデザインが取り入れられていた。これは建築時に敷地内で掘り起こされた石を再利用したものだという。もともとこの土地にあったものが意匠的に取り入れられることで、風土に溶け込んだ景観をつくり出していた。
また、薪ストーブのある暮らしならではの薪棚も庭を彩る。近隣の里山整備で出た木材をもらってきて、あかい工房の薪割り機を借りて施主自らが用意しているのだという。さらに家庭菜園のスペースもあり、家と土地、素材と手間がつながる暮らしがそこにあった。

建築時に敷地内で掘り起こされた竜山石を再利用した外構計画

石垣にも竜山石を活用
竜山石の採石場を訪ねて
かつて高砂市の主要産業だった採石業も、現在残る山元はわずか3軒。そのひとつ、明治5年創業の老舗「株式会社松下石材店」を訪ね、社長の松下尚平さんに話を伺った。

山肌が切り立つ採石場を見学し、松下社長の話を伺った
竜山石はおよそ1億年前の火山活動でできた凝灰岩で、主に高砂市阿弥陀地域で採掘されている。その歴史は古く、古墳時代に石棺として使われていたという史実が残っており、東は滋賀県、西は山口県までの広範囲で古墳から発掘されている。1700年ものあいだ同じ場所から採石され続けている石材は国内で唯一、竜山石だけだという。
特徴は、ひとつの山から青・黄・赤の3色が採れること。本来の色は青色だが、生成過程で熱を受け、酸化反応によって青→黄→赤へと変化する。赤色は山の表面にしか現れず、かつ様々な条件が揃わなければできないため、今では新たに採れることはなく、大変貴重だという。松下石材店では古民家の取り壊し時に石を救出し、再利用することもあるそうだ。

ひとつの山から青・黄・赤の3色が採れる
凝灰岩は吸水性が高く、コーヒーのように色のついた飲み物をこぼすとシミになるが、薄めた漂白剤で落とせることもあり、多少であれば素人でもメンテナンスも可能。撥水剤を塗布して使う場合もある。松下社長は「むしろ使い込んで経年変化を楽しむのがおすすめです」と話す。
その吸水性と揮発性から調湿機能もあり、古くから奈良や京都にある社寺の基礎に多く使われ、民家でも延石や板石、井戸の井筒・たらいなどに利用されている。
この話を聞いた大塚工務店の大塚社長は「木みたいな扱い方ができるんだな」と感想をつぶやいた。竜山石は木材と同じく、まさに使い込むほどに風合いが増す素材なのだ。
現代の木造住宅において、構造材として使われることはほとんどない。現在は主に壁材・床材等の建築材として使用されている竜山石は、上がり框・薪ストーブの炉台・表札など、アクセントとしての使い方も再び注目されている。

切り出した石の加工場

オーダーに応じた研磨やびしゃんの仕上げに対応している
きめ細かく優しい肌触りとパステル調の色合いが特徴で、和洋問わず空間を上質に彩る。国内にとどまらず海外の商業施設にまで広がる活用例を見せてもらうと、建材としての石が今も新しい可能性を拓いていることを感じた。石材業者をはじめ工務店、設計事務所等から継続的に注文が寄せられるケースも多いようだ。また、神社仏閣や近代建築にも多く利用されていることから、その修復・修繕工事にも対応できる技術も持ち合わせている。松下石材店では作り置きの在庫はなく、全てオリジナルで受注生産されている。
また、今回のような視察の受け入れや、地域の学校などと協働して新しい竜山石の可能性を探る活動も積極的に行われている。「1700年続く竜山石の歴史と伝統を絶やしてはならない」という社長の強い思いが伝わってきた。
視察を終えて
今回の視察であらためて感じたのは、家づくりにおいて「素材を選ぶ」という行為は、単なる性能や意匠の問題ではないということだ。竜山石は、1億年という時間をかけて堆積し、1700年もの間、人々の暮らしとともに使われ続けてきた存在だった。その石を建築に活用していくことは、この土地の風土や伝統を未来へと継いでいくことに他ならない。
採石場を前にしたときに感じたのは、素材そのものが語りかけてくる「この土地の声」だった。それをどう設計に活かすのか、どう日常の中に取り込むのかは、工務店や設計者に課された使命でもあると言える。素材を通じて地域とつながることで、家がただの器ではなく、この土地の風土の記憶を刻む場となっていく。その営みを続けることが、HOUSE for LOCALの目指す「風土と暮らす木の家」づくりに繋がると強く感じた。